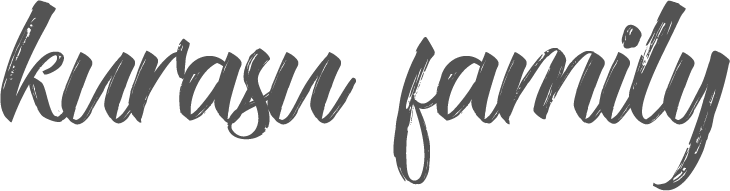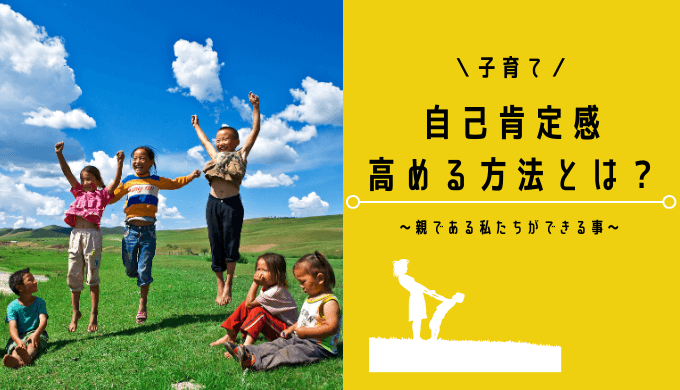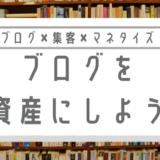子育てになんだか漠然とした不安を感じたことはありませんか?
他の子供と比べて落ち込んでしまったり、本来悩まなくて良いことで悩んでいることも多いように感じています。最近では「自己肯定感」という言葉をよく耳にするようになりました。
自己肯定感という言葉は聞いた事があるけど、いまいち意味がわからない。
自己肯定感を高めるにはどんな事をすれば良いの?
この記事では、子供の自己肯定感の重要性と自己肯定感を高める方法ついてまとめています。
子供の自己肯定感を高めるには親の対応はとても重要で、子供に対する言動が大きく影響するとも言われています。
しかし、私たち親も一人間。完璧な人なんていません。それが子育てとなれば、初めてのことだらけ。正解がわからない中で、たくさん悩みながら子育てをしているのも事実です。
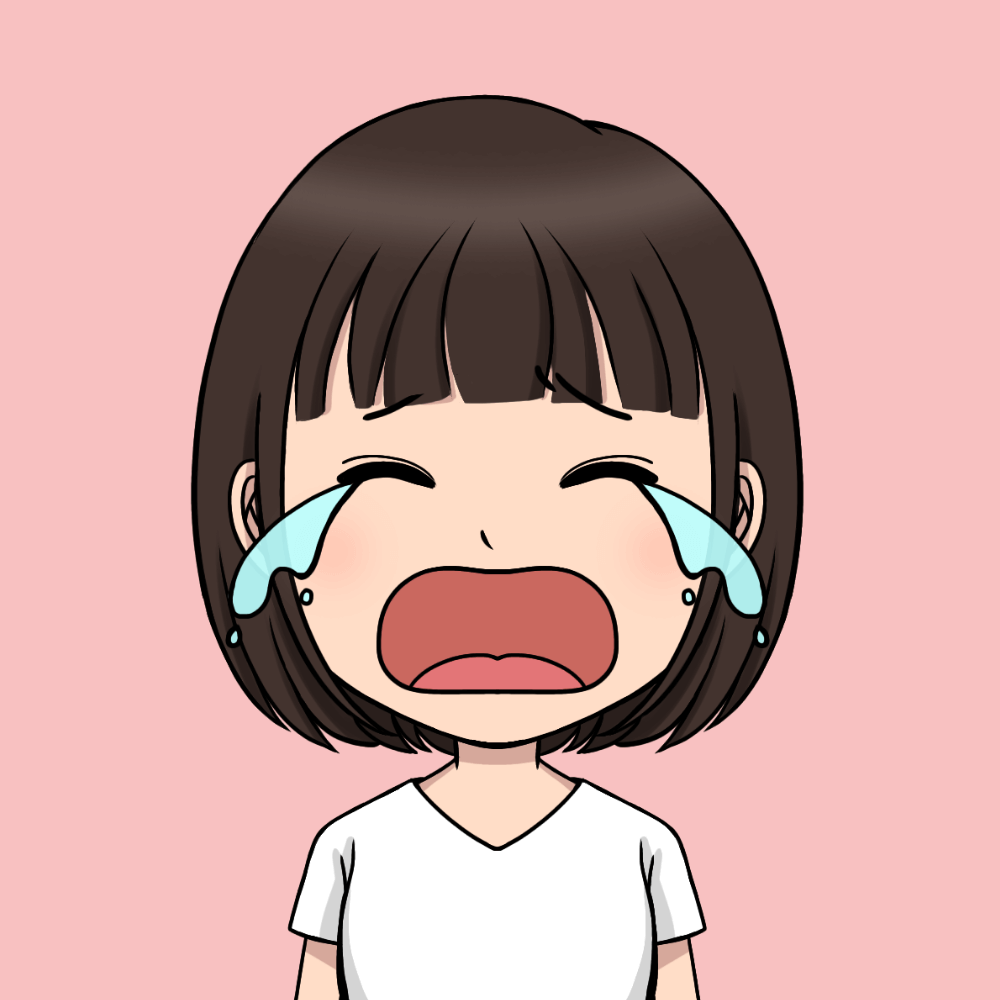
子供のしつけや友達とのトラブル、こんな時はどうすればいいの?とわからない事だらけ。子育てはイレギュラーばかりなんです!
- 自己肯定感について知ることができる
- 子育てをする上で大切なことを知る事ができる
- 子育ての漠然とした悩みや不安の解決の糸口を見つける事ができる
私たち日本人は諸外国の人に比べ、自己肯定感が低い傾向にあるということをご存知でしょうか。自己肯定感が低下しがちな日本人だからこそ、なぜ自己肯定感が低くなってしまうのかを理解し、自己肯定感を高めるメリットやその方法を、まずは”知る”事がとても大切です。
子育てに正解はありません。自己肯定感を育てる上で大切なのは、子供そのままの存在を受け入れ、そのままでいいんだよ、と伝え続けることなのです。
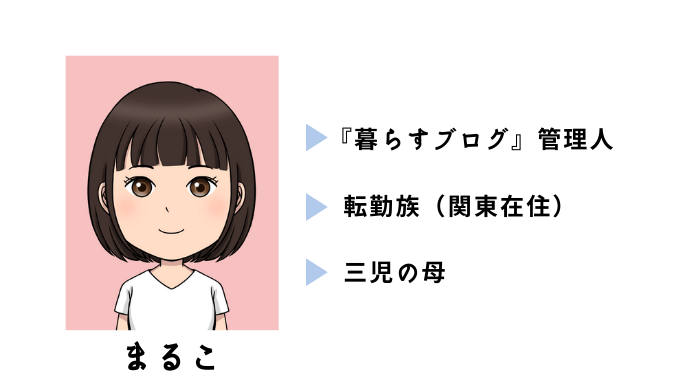
目次
自己肯定感とは?

自己肯定感とは、自分の存在を肯定的に受け止められる感覚のことです。
子供自身が自分であることに満足(自分が大好き)で、尚且つ価値ある存在として受け入れられることを自己肯定感といいます。自己肯定感は子どもが成長していくうえでとても大切な感情です。
そしてこれは、子供たちにとって生きていく上での重要な軸となり、生きていく上でのエネルギーそのものです。
- お父さんお母さんにとって自分は大切な存在
- 自分には価値がある
- やればできる!頑張ってみよう!
このようなことを、子供は感じる事ができているのでしょうか?
自己肯定感を育てるにあたり、とても大切な事があります。それは、他者との比較に基づくものではなく、”無条件”で子供を認めてあげる事です。
そうする事で、情緒の安定につながり、いかなる状況でも物事をポジティブに捉えることができるようになります。
自己肯定感は、自分の心を守ってくれる大きな柱のようなものと考えてみてください。大きな柱がしっかりと強く倒れずにいてくれてさえいれば、雨風嵐の日にだって電柱が倒れてしまう事はありません。
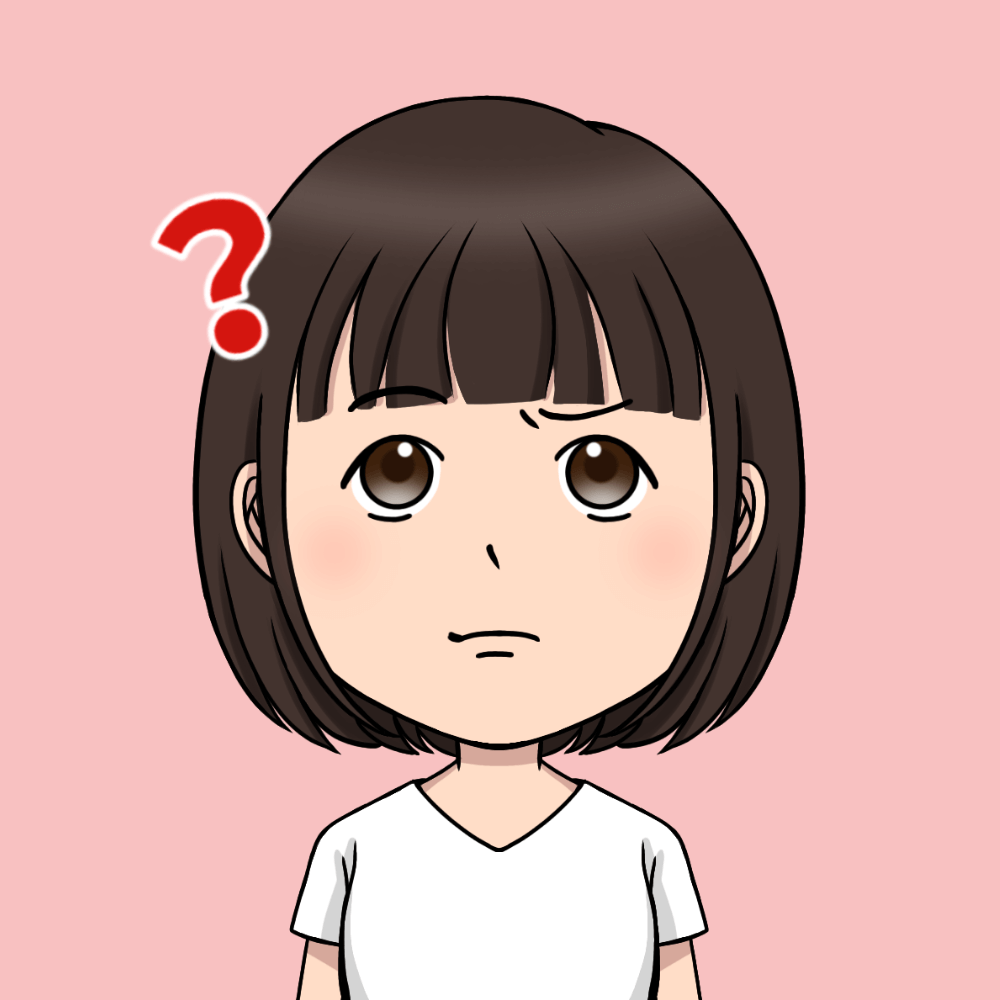
自己肯定感を育てる事が大切な事はわかってきたけど、実際にはどんな違いがあるんだろう?
自己肯定感が高いとどうなるの?
自己肯定感が強い子供は、
- 情緒が安定し、物事をポジティブに捉える事ができる。
- 失敗を恐れず、何度でも挑戦しようという気持ちが湧いてくる。
- 自分を信じることで、他者への寛容さが生まれ、対人関係においてもいい影響を及ぼす。
- 自分の個性や長所に気づく事ができる。他からの評価がなくとも、正しく評価することができる。
日々の生活の中でも、物事に対して幸せを感じやすくなります。
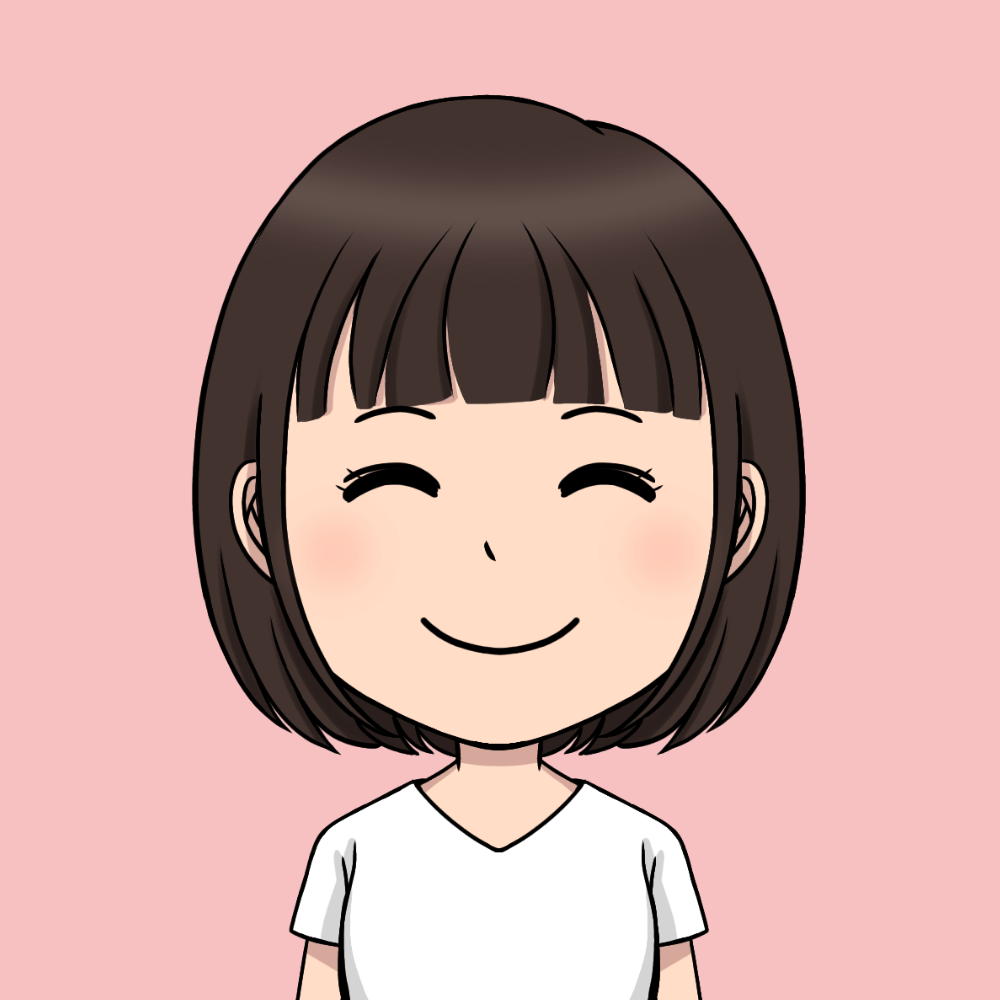
ハッピーは作れる!子供たちと過ごしていく中でいつも感じている事です。
自己肯定感が低いとどうなるの?
自己肯定感の低い子供は、
- 情緒が不安定になり、物事とをネガティブに捉えるようになる。
- 嫉妬心や劣等感を強く抱いてしまう。
- 自分に自信が持てない。
- チャレンジ精神や好奇心、積極性がなくなる。何事に対しても消極的になり、挑戦していたことを途中で諦めてしまうことも。
ここで一番避けたいのは、自分を否定する癖が付いてしまうことです。挑戦するのを恐れたり、成功に対してもゆがんだ考えをもってしまうようにもなります。
自己肯定感が低くなってしまう原因とは?

親が子供の話を聞かない
子供の話を聞く機会を作らずにいると、子供はいつの間にか、お父さんお母さんは自分に興味がない、どうせ分かってもらえない、という負の感情を持つようになります。
親が子供の行動を決定する
子供は成長に合わせて自分で選択することが増えていきますが、いつまで経っても物事を親が決めてしまうと、自分の意見は尊重されないと思うようになります。これは、”自分は大事に思われていない”と自己否定の感情を生むことにも繋がります。
何事も結果でしか判断しない
「上手・下手」「できる・できない」で判断していると、自己肯定感は生まれません。子供は、やってみたい!という感情や、挑戦してみようという気持ちで物事に取り組んでいます。優劣を評価するのではなく、行為そのものを伝えてあげるだけで子供は十分に満たされる、という事です。
絵を描くにも、運動をするにも、
”出来を褒める→行為を認める”という事を意識してみてください。
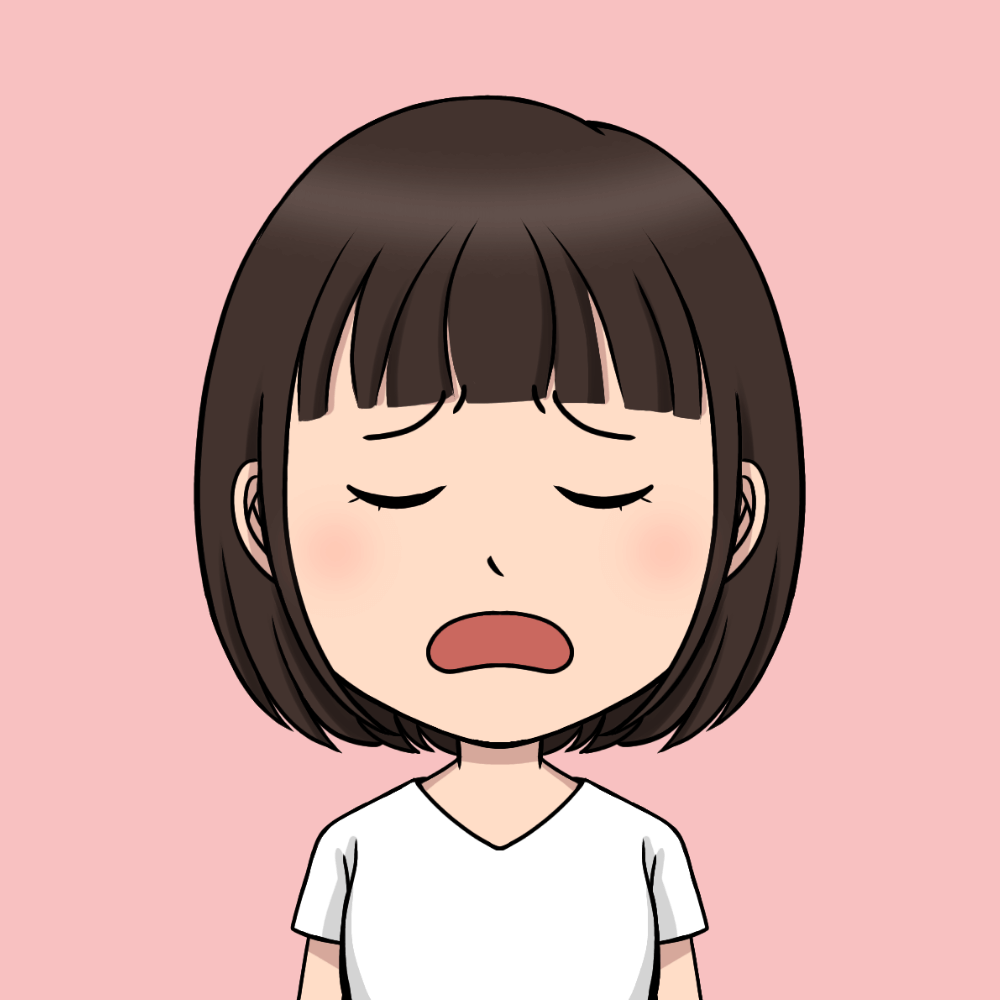
上手だね!すごいね!
これは私もよく言ってしまいます・・・(反省)
褒められる事が目的となってしまうため、言葉がけには注意が必要です。
必要以上の厳しいしつけ
しつけのラインは各家庭によって異なりますが、必要以上に厳しくしつけをしてしまうことはよくありません。
子供にとって親は唯一の味方であり、心のよりどころです。頼れる人から必要以上に厳しくされると、自分は大事な存在ではないと感じるようになってきます。
厳しさのなかにも親としての優しさや思いやりを持って接していると、子供ながらにその思いを汲み取る事ができるようになってきます。
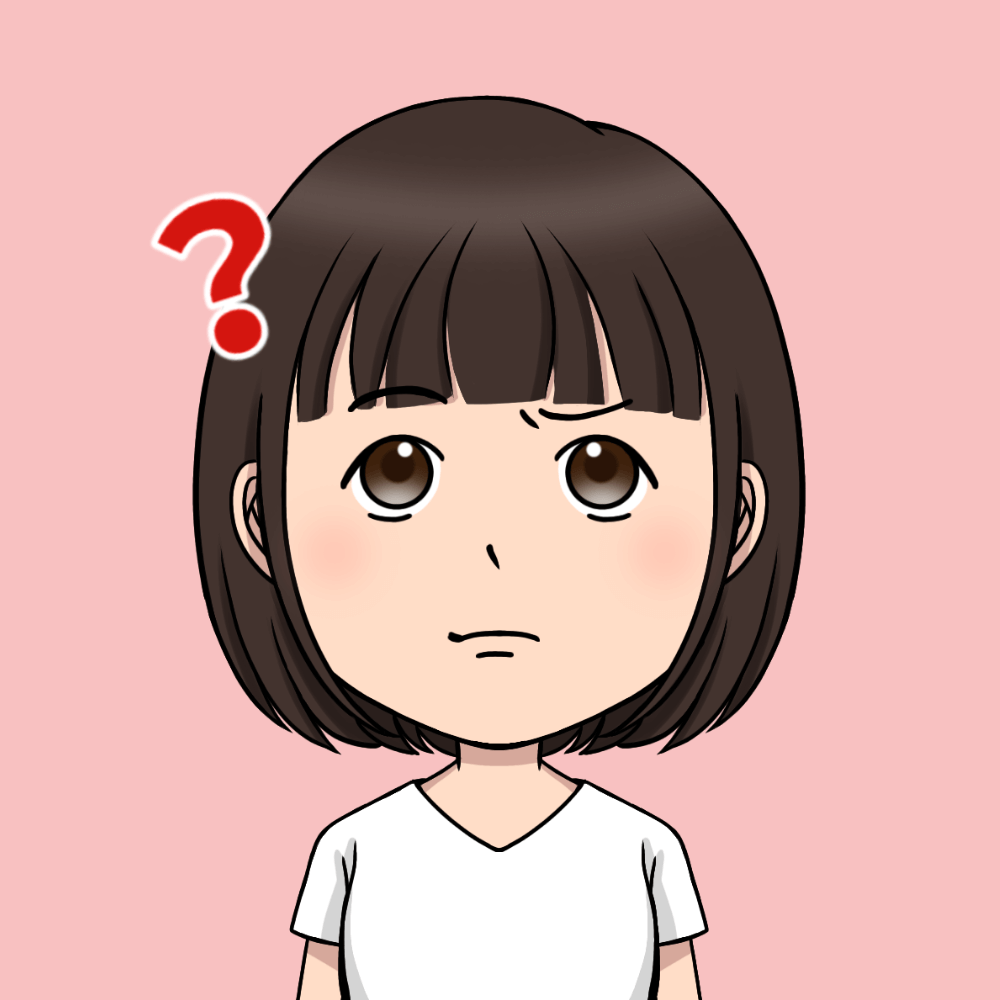
実際に子供の自己肯定感を高めたい時はどのようなことを気をつければ良いんだろう?
自己肯定感を高めるために

次の行動への言葉がけ

失敗をしたりしても「頑張ったね!」「大丈夫だよ」「次頑張ろう」と、次に繋がる声かけをします。
「次はこうしたい」など、子供のチャレンジや次のステップを一緒にイメージする事ができると、子供ながらにそのイメージを実現したいという気持ちが起こり、やる気や意欲が自然と身についていきます。
悪いことをした時には気持ちに寄り添う

何か間違ったり、いけないことをしたときは「これから気をつけよう」「やらないようにしようね」と寄り添うことも大切です。「これが嫌だったね」「こうするといいかな?」など、子供の気持ちに共感してあげられるといいでしょう。
しかし、子供が悪いことをした時、つい怒ってしまいますよね。とっさに叱ってしまう事も少なくありません。
ですが、悪さの裏柄には子供からのサインが隠れている事もあります。悪いことをしたらそれを指摘して注意することはもちろん必要ですが、一歩立ち止まりなぜ今この行為をしたんだろう?と、子供の目線で考えてみてください。
子どもを否定しない

何かに挑戦する際、結果ばかりに目が向いてしまい、頑張ったことを否定したり、心配するあまり自分で何もさせなかったりすると、子どもは自分を否定するようになってしまいます。子供の自信を失わせてしまう対応の例がこちら。
- 失敗を責める
- 他の子と比較する
- 行為そのものを不定する
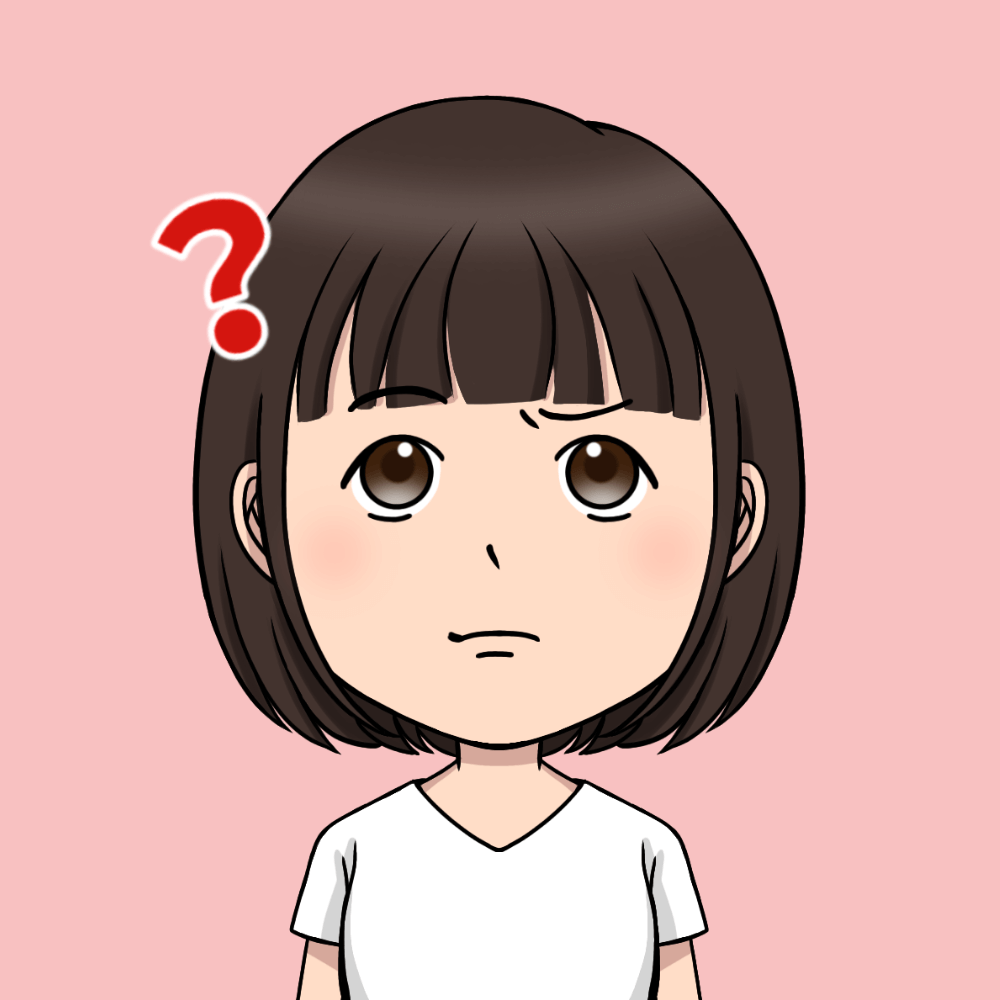
こんな場合は、どんな言葉がけがいいんだろう?
- 失敗を責める→どうやったら成功できるかな?と一緒に考えてみる
- 他の子と比較する→比較しない
- 行為そのものを不定する→挑戦した事を認める
些細なことでも毎日の積み重ねで、子供の中に自分が大切な存在である、という自己肯定感が育ってきます。子どもを否定することなく、子どもの考えや行動を受け入れてあげることが自己肯定感を育てる上でとても大切です。
【まとめ】そのままのあなたが大好きと伝えよう

これまで書いてきたように、子供の自己肯定感を高めることで多くの問題や困難に強い気持ちで立ち向かう事ができます。
ここで一番大切なことは、良いも悪いも含めて子供を受け入れ、”そのままであなたで良いよ大好きだよ”と存在を認めてあげる事です。そうする事で、自然と子供の自己肯定感は高まり、物事をポジティブに捉えられるようになります。また、子供の精神的な安定だけでなく、これから立ちはだかるであろう大きな壁にも強い気持ちで立ち向かっていく事ができるようにもなります。
自己肯定感は子供のこれからの人生に大きな影響を与える人生の鍵にもなり得るものです。お父さんお母さんの「大丈夫」の一言で、子供は大きな安心感を覚えます。親である私たちも一緒に、子供が成長していく過程を楽しみながら子育てできると良いですね!
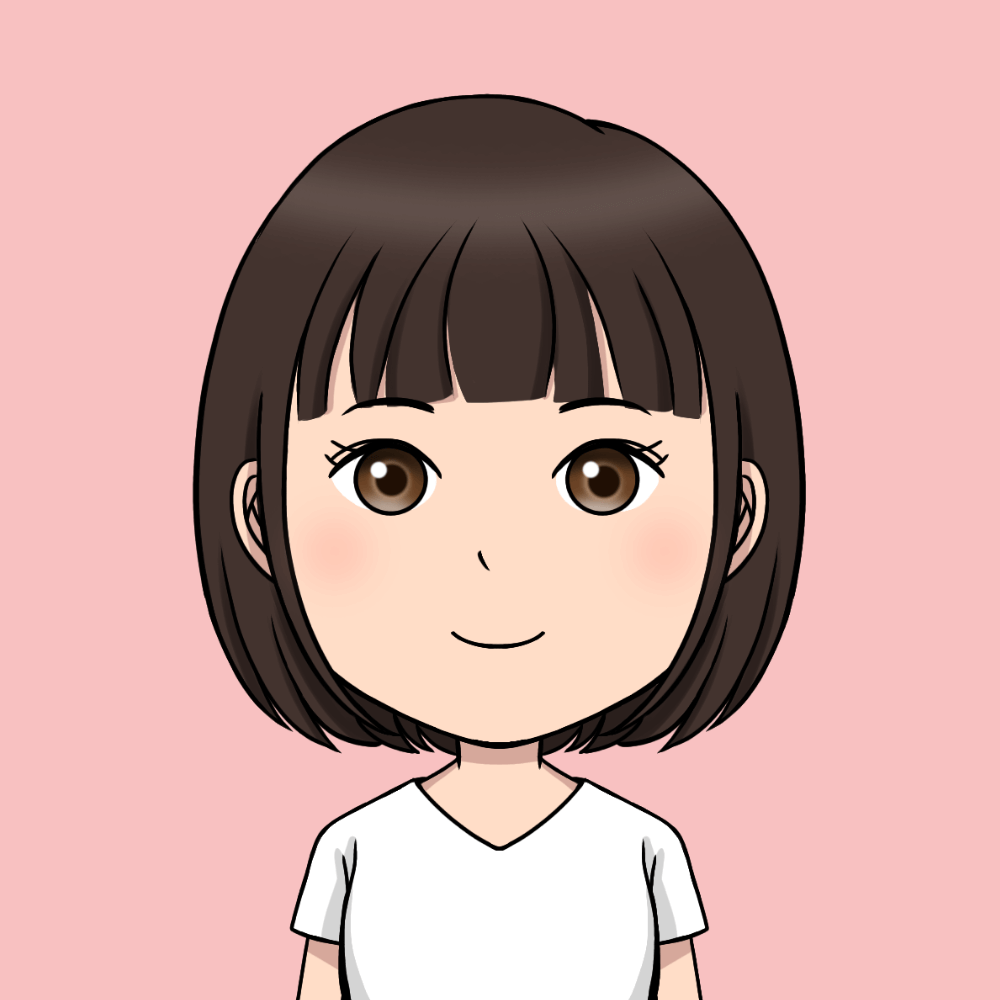
子育て歴8年。まるこもまだまだ子育てひよっこ。日々のバタバタに追われる毎日ですが、できるだけポジティブな気持ちで子育てしていきたいですね!