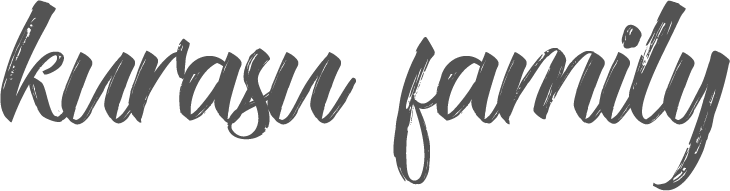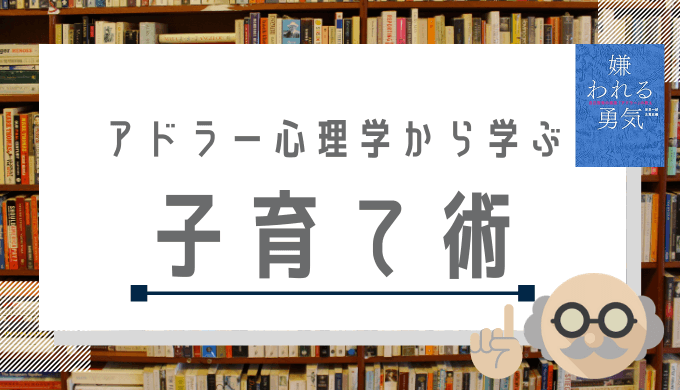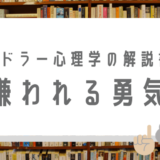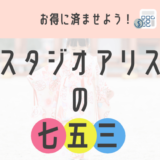皆さんは、人から嫌われることについてどう感じますか?
なるべくなら嫌われたくない、できるだけたくさんの人に好かれたい・・・
そんな風に感じる人も多いと思います。
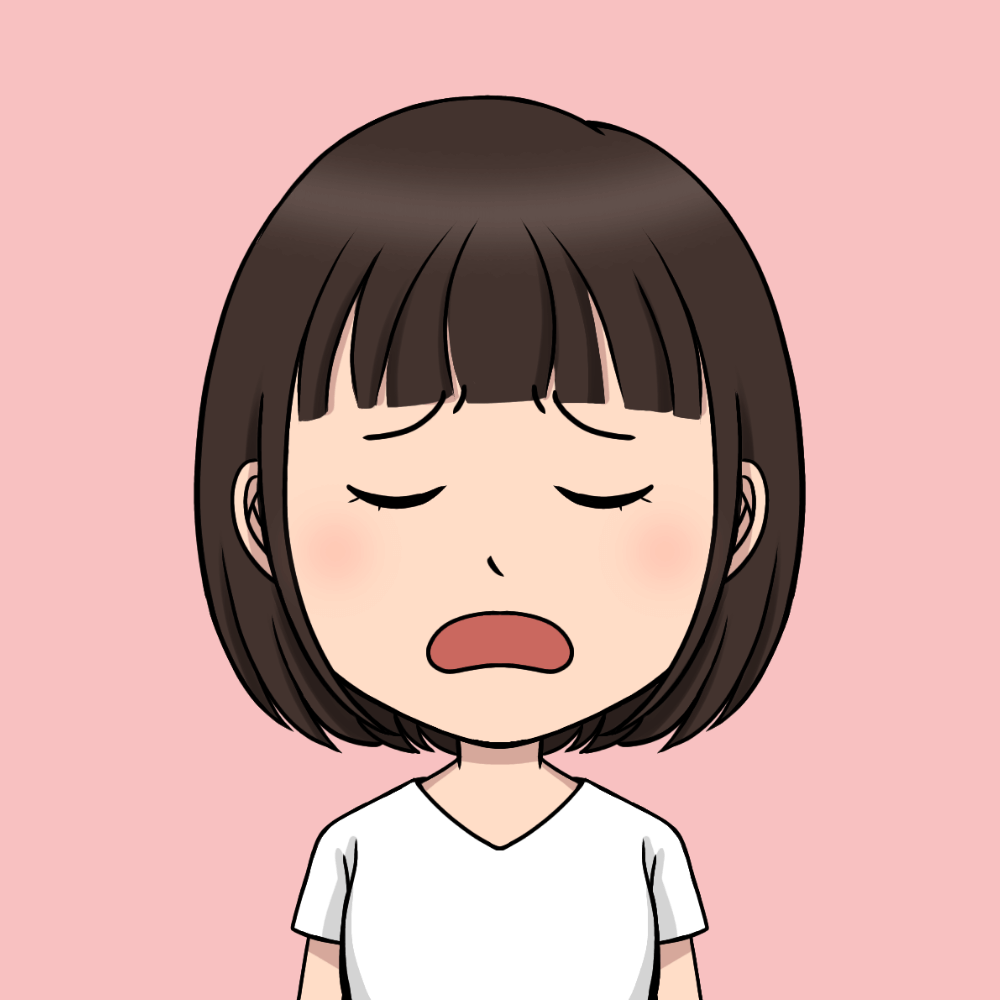
私自身も、ずっとそう感じて生きてきました。
そんな中、人から嫌われたくないと思っていた私のこれまでの価値観を覆すきっかけとなった本があります。少し大げさに言えば、人生観が変わったとも感じています。
\その本がこちら/
そこで今回は、アドラー心理学を解説した書籍『嫌われる勇気』を読んで学んだことについてまとめました。この本は、生きていく上でだけではなく、子育てをする上でも非常に参考になる考え方がたくさん詰まった一冊です。私なりの解釈も含めながら、子育てに活かせる考え方についても書いています。
- なんだか生きづらい
- 心が疲れているな
- 子育てがうまくいかない
- 子どもが言うことを聞いてくれない
そんなモヤモヤに悩む方は、是非最後まで読んでみてください。
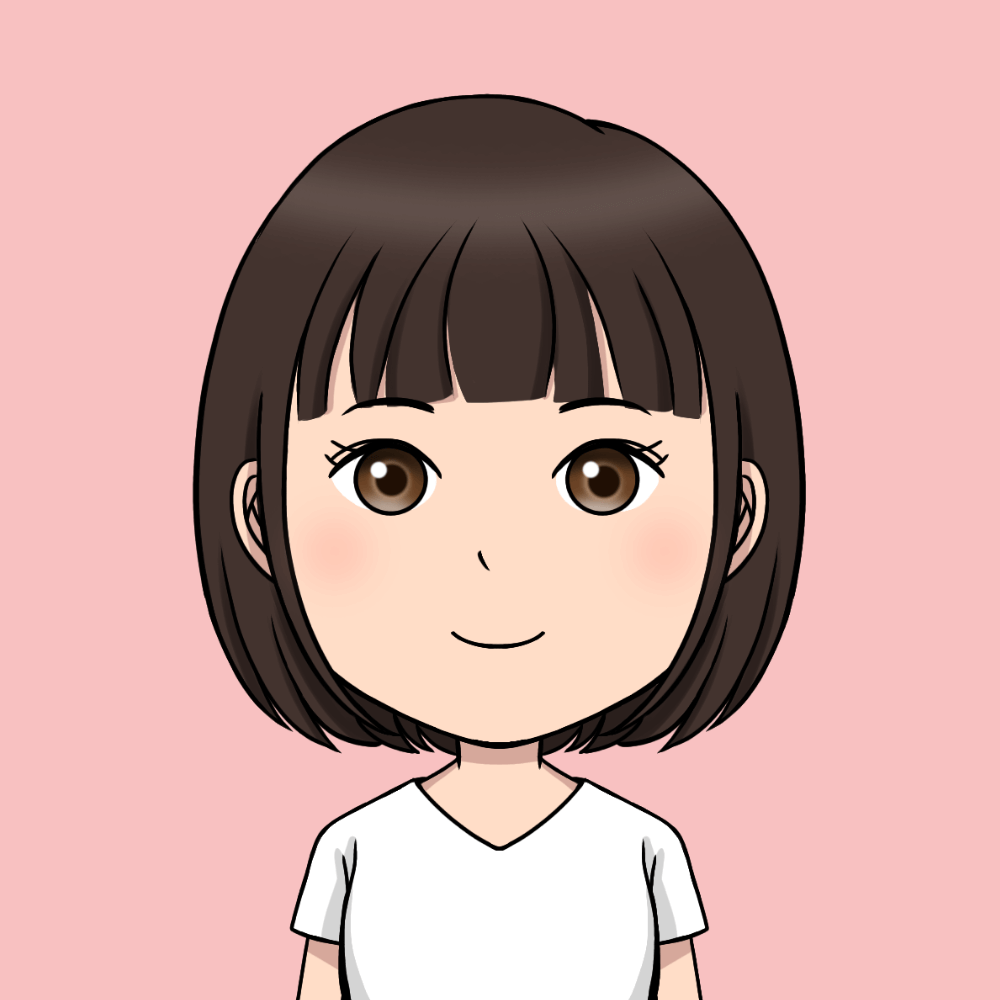
毎日のモヤモヤを解消できるきっかけになれば嬉しいです。
- アドラー心理学について理解できる
- アドラー心理学に基づいて考えられる子育て術を知ることできる
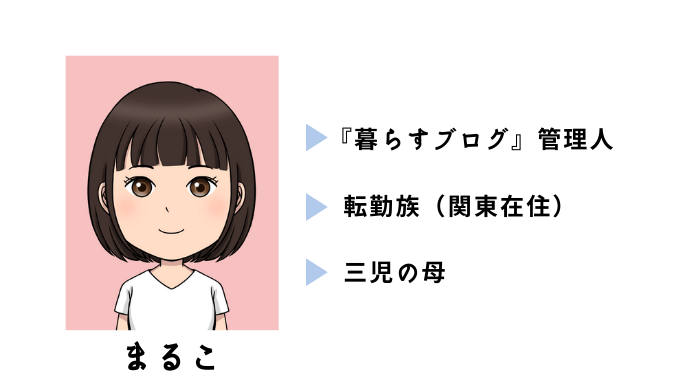
目次
『嫌われる勇気ー自己啓発の源流「アドラー」の教え』とは?

『嫌われる勇気ー自己啓発の源流「アドラー」の教え』(以下『嫌われる勇気』)は、アドラー心理学を解説した書籍です。アドラー心理学とは、世界的な心理学者アルフレッド・アドラーが、20世紀の初頭「アドラー心理学」と呼ばれる心理学を創唱したもの。
この本は、2013年に出版され、累計発行部数は200万部突破のベストセラーとなり、ドラマ化されるほど大ヒットしました。
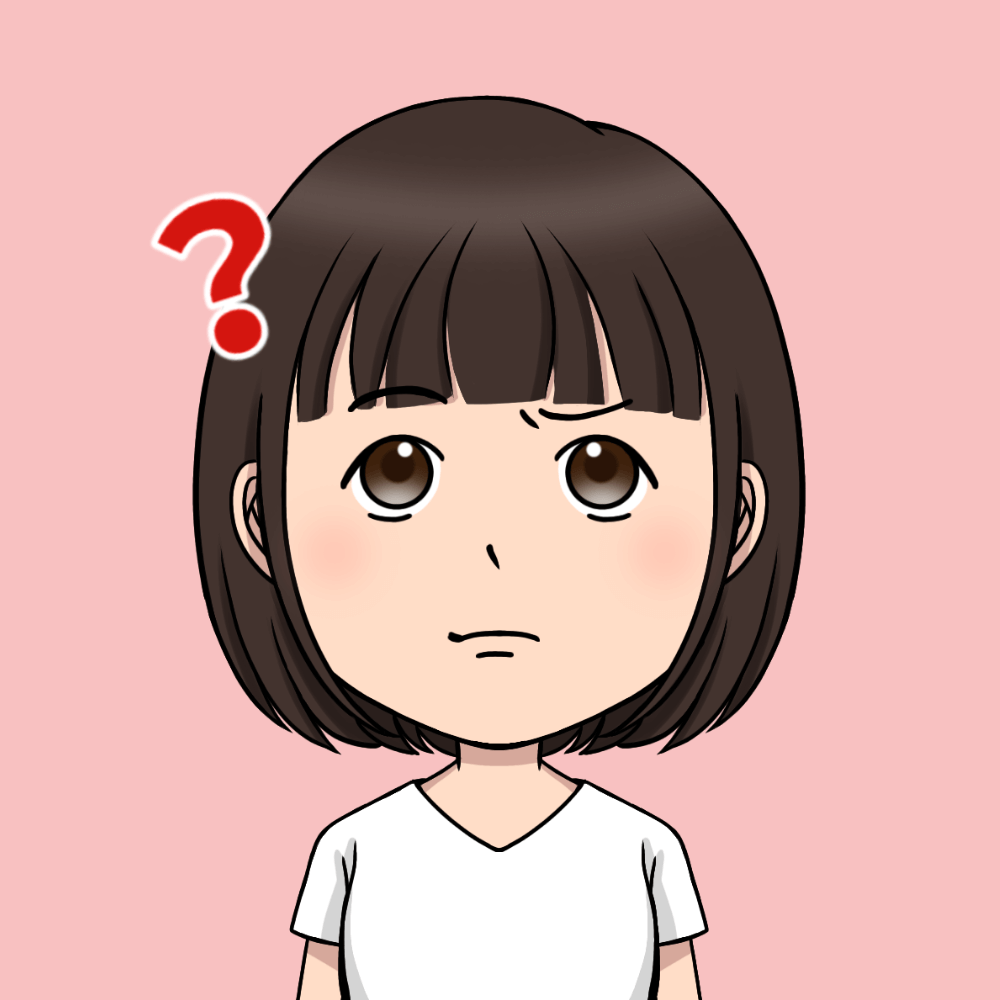
私は本を知る前にドラマを見たのですが、ドラマは正直「うーん?微妙かな・・」と言った感想でした。理由の一つが、アドラー心理学の教えを貫く主人公に、冷たい印象を持ったからです。
書籍『嫌われる勇気』で学んだアドラー心理学はこれまでの人生観が覆るほど衝撃的な内容ですが、決して「冷たく」感じるものではありませんでした。
『嫌われる勇気』は以下5つの構成で作られています。(私が解釈したものなので、実際の構成とは異なります。)
- 原因論ではなく目的論
- 人の悩みの全ては対人関係
- 課題の分離
- 対人関係=共同体感覚
- 生きる意味
要約すると、人のすべての悩みの原因は対人関係であり、他の人から認められたいという承認欲求が人の悩みを引き起こしているというもの。周りから嫌われないようにする生き方こそ不自由極まりないものであるとアドラーはいいます。
そこでこの本では、対人関係の問題を解決し、すべての悩みから解放されるには、「嫌われる勇気を持ちなさい」ということが書かれています。
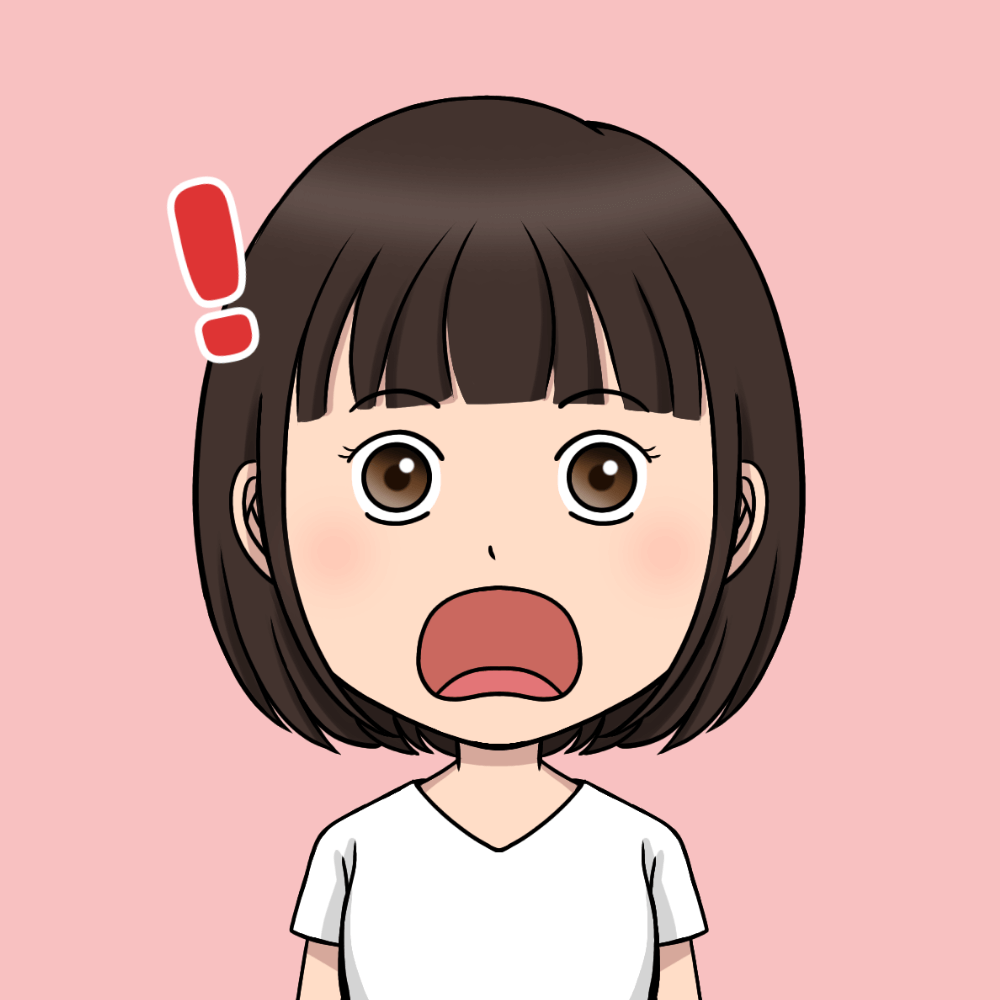
嫌われる勇気!?なるべくなら人から嫌われたくないと生きていただけに、その内容はとても衝撃的でした!
また、この本の中には人が快適に生きていく上で参考となる考え方がいくつも記載されています。
- 問題は世界がどうあるかではなく、あなたがどうであるか
- 自分を変えることができるのは、自分しかいない
- 人生とは誰かに与えられるものではなく、自ら選択するものであり、自分がどう生きるかを選ぶのは自分である
- 他の人から嫌われる勇気を持つことで、自分らしく自由に生きることができる
これは子育てをする上でも非常に大きなヒントになります。
そこで、次の章では実際に子育てをする上で活かしていきたいアドラー心理学の考え方についてまとめました。
「嫌われる勇気」から学ぶ子育て術

この章では、上に挙げた5つの項目のうち、
- 人の悩みの全ては対人関係
- 課題の分離
- 対人関係=共同体感覚
この3つに焦点を当てて解説しています。
\5つのすべての項目はこちらから/
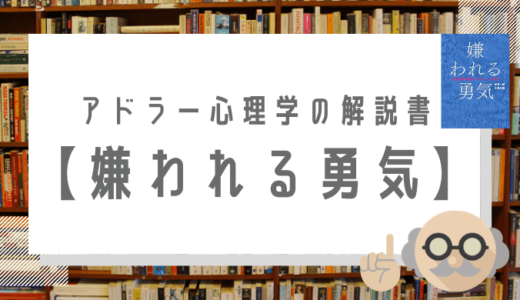 アドラー心理学の解説書『嫌われる勇気』を読んで
アドラー心理学の解説書『嫌われる勇気』を読んで
アドラー心理学は、アドラー個人の思想であり、それを生きていく上でどう活かすのかは、個人の自由。私自身この考え方に共感し、実践している身ではありますが、感じ方や考え方は人によって異なるため、大切なのは、自分なりに考え、選択していく必要があると言うことです。自分の価値観と似ているもの、共感できるものがないか、ぜひ探してみてくださいね。
【人の悩みの全ては対人関係】健全な劣等感を活かす

アドラー心理学では、「人間の悩みはすべて対人関係の悩み」と断言されています。ここで言う人間とは【子育て】、対人関係とは【他者比較】を指します。
子育てをしている中で、我が子と他の子どもの成長とを比べては、「劣等感」を感じてはいませんか?子育ての悩みの多くは、この「劣等感」からきていると言っても過言ではありません。
人間の中にある「劣等感」をうまく使えば、子どもの努力や大きな成長、次へ挑戦へのきっかけを促すこともできます。この場合の劣等感とは、他者との比較からくるものではなく、『理想の自分』との比較から生まれる「健全な劣等感」を指します。「健全な劣等感」を活かし、前に進もうと成長する姿にこそ、価値があると記されています。
もうすぐ2歳になる我が子が、なかなか言葉がでないことに悩むお母さん。上手に会話できる周りの子と比べては「なんでうちの子だけ・・・」と不安になる。
ここで分かるのは、親が勝手に周りの子と比べて劣等感を抱いてしまっているということ。アドラー心理学を元に考えると、これは主観的な思い込みであり、「健全な劣等感」ではないことがわかります。
大切なのは、今よりも前に進もうとする意欲に価値があるということ。
昨日よりも今日、今日よりも明日、子どもができるようになることは確実に増えています。
それは言葉においても同じ。「パパ」「ママ」など、1歳の時には言えなかった言葉が今は言えるようになってはいませんか?発語をしようと口を開けてはいませんか?慌ただしくすぎる日々の中では、子どもの小さな成長をどうしても忘れがちです。
小さいながらもその成長を感じながら、前に進もうと頑張る子どもを見守ってあげられると、これまでの悩みも少し解決の糸口が見えてくるのではないでしょうか。
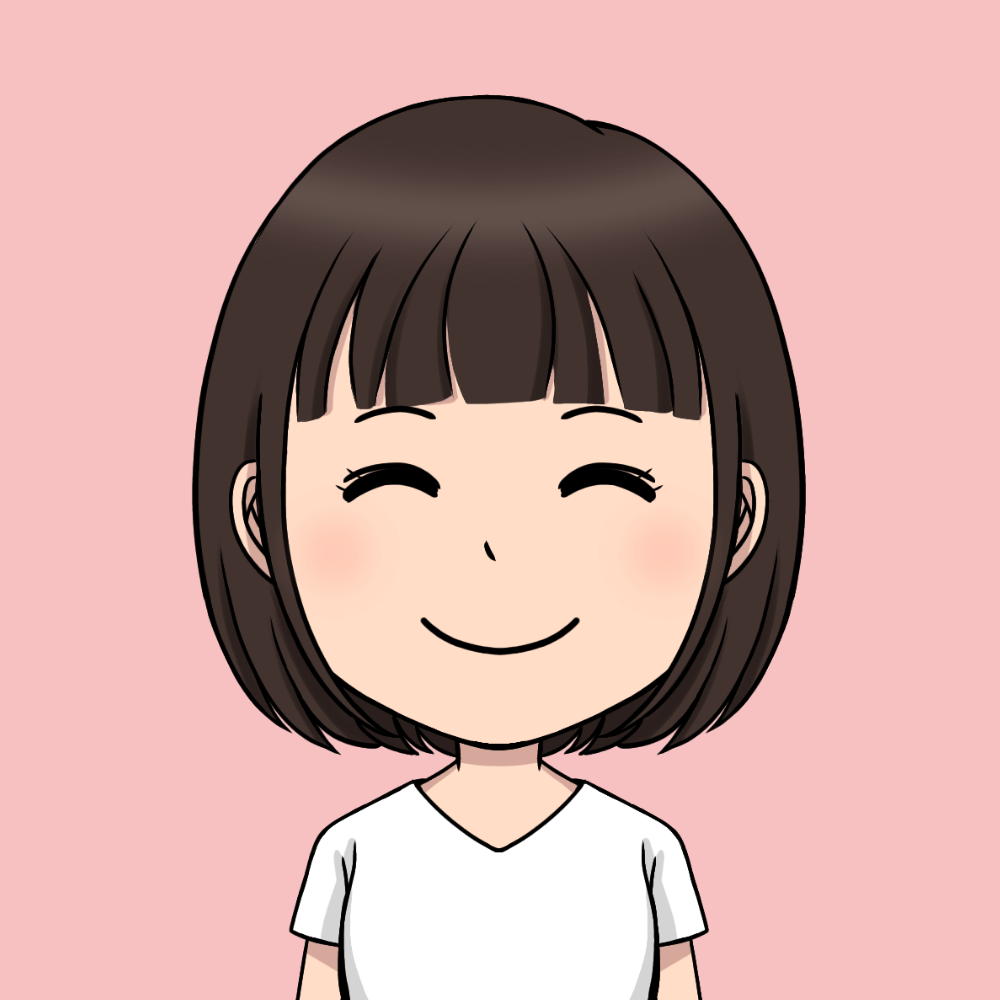
親も子どもと一緒に成長していきたいですね!
小学生になり、本格的に学習がスタート。勉強に苦手意識を持っており、初めてのテストでは50点しか取れなかった。その後のテストでもいつも点数が悪く、「なんで自分は100点取れないんだろう・・・」と落ち込む。仲良しの友達が100点を取ったことを聞いて、「自分は勉強ができない」「どうせ頑張っても無駄だ」と友達に対して劣等感を抱く。
ここでもアドラー心理学を元に考えると、友達のテストの点数に対するものは「健全な劣等感」ではないことがわかります。
「健全な劣等感」であれば、勉強するきっかけや、100点を取れるように努力しようとする姿勢、意欲を燃やすきっかけを作ることができます。
この時、親である私たちに求められるのは、子どもが「健全な劣等感」をうまく使い、勉強に対して前向きに取り組むことができるよう見守ること。友達も頑張っていることを励みにできるような言葉がけを心がけてください。
友達と比べては「なんであなたはできないの?」などと批判的なことを言わないようにしましょうね。
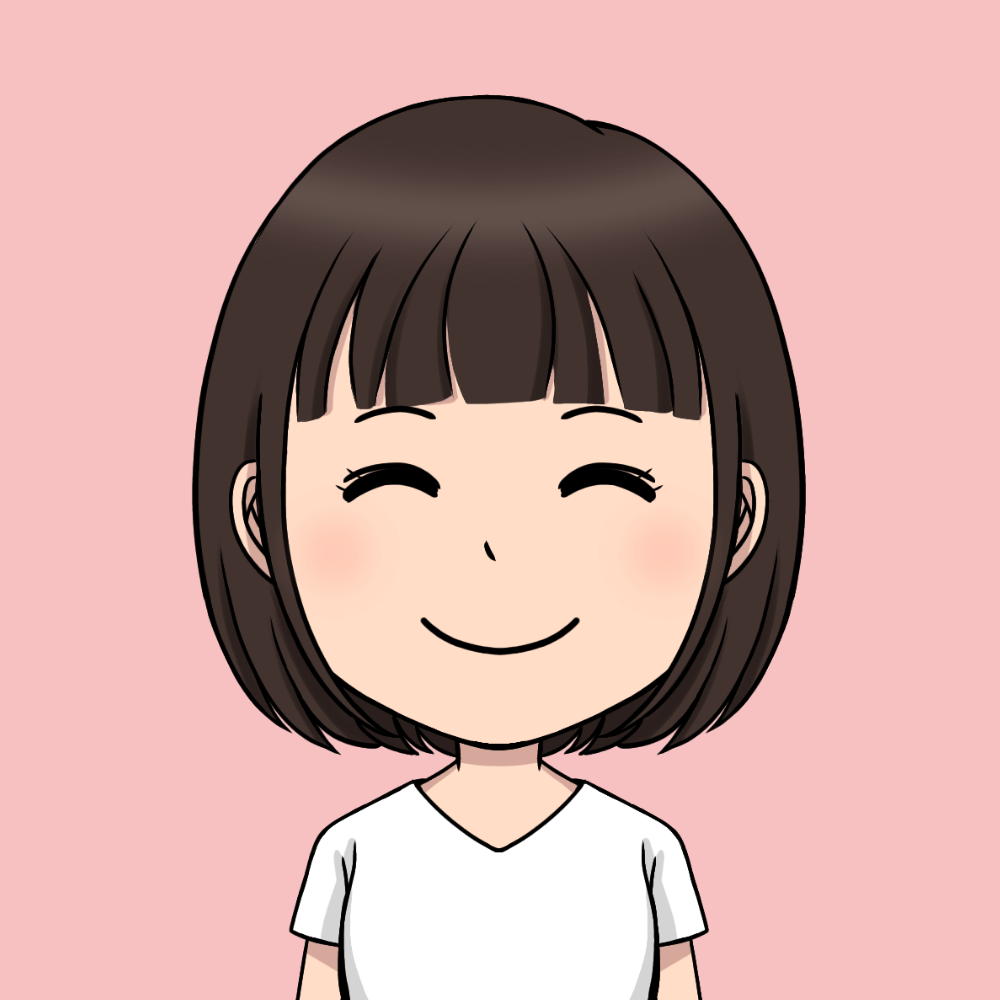
勉強に対して意欲的に行うきっかけになるよう、サポートしていきたいですね!
【課題の分離】親の課題と子どもの課題

「課題の分離」とは、自分と子どもの課題を、切り離して考え、お互いに介入しないようにすることです。子どもが言うことを聞かない時、スムーズに行動しない時には、まずそれは誰の課題なのかを考えてみましょう。
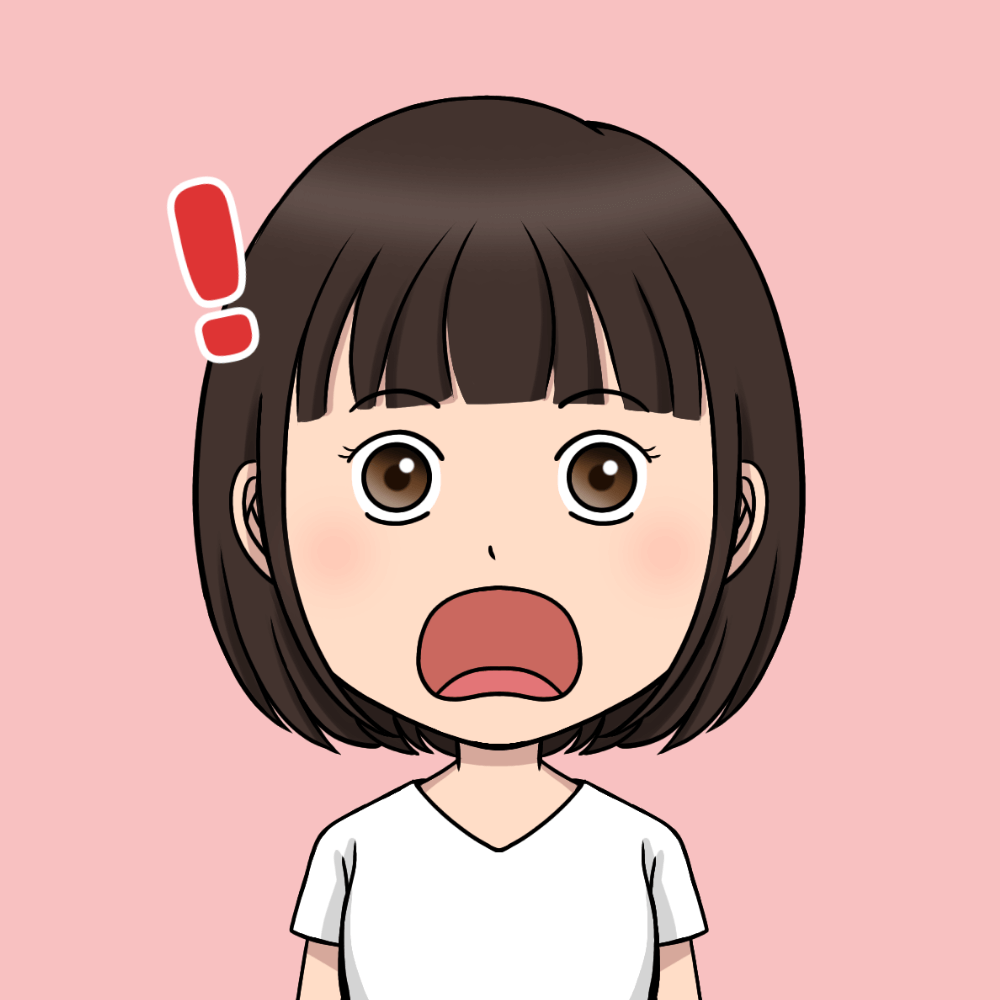
課題の分離は、この本で最も衝撃的、かつ最も納得のいく考え方でした。
世の中、自分にはどうすることもできないことで溢れています。
子育てもその一つ。親である私たちの思いとは裏腹に、「準備や支度をするのが遅い」「友達に手を出してしまう」「好き嫌いが多い」など、子どもにおいても、それぞれの課題があるのも事実です。
私自身、正解のない問いにたくさん悩んできましたが、それは誰の課題なのかと言う「課題の分離」という考え方を取り入れることで、これまでの子育ての悩みは解消し、自分でも驚くほど気持ちが楽になりました。
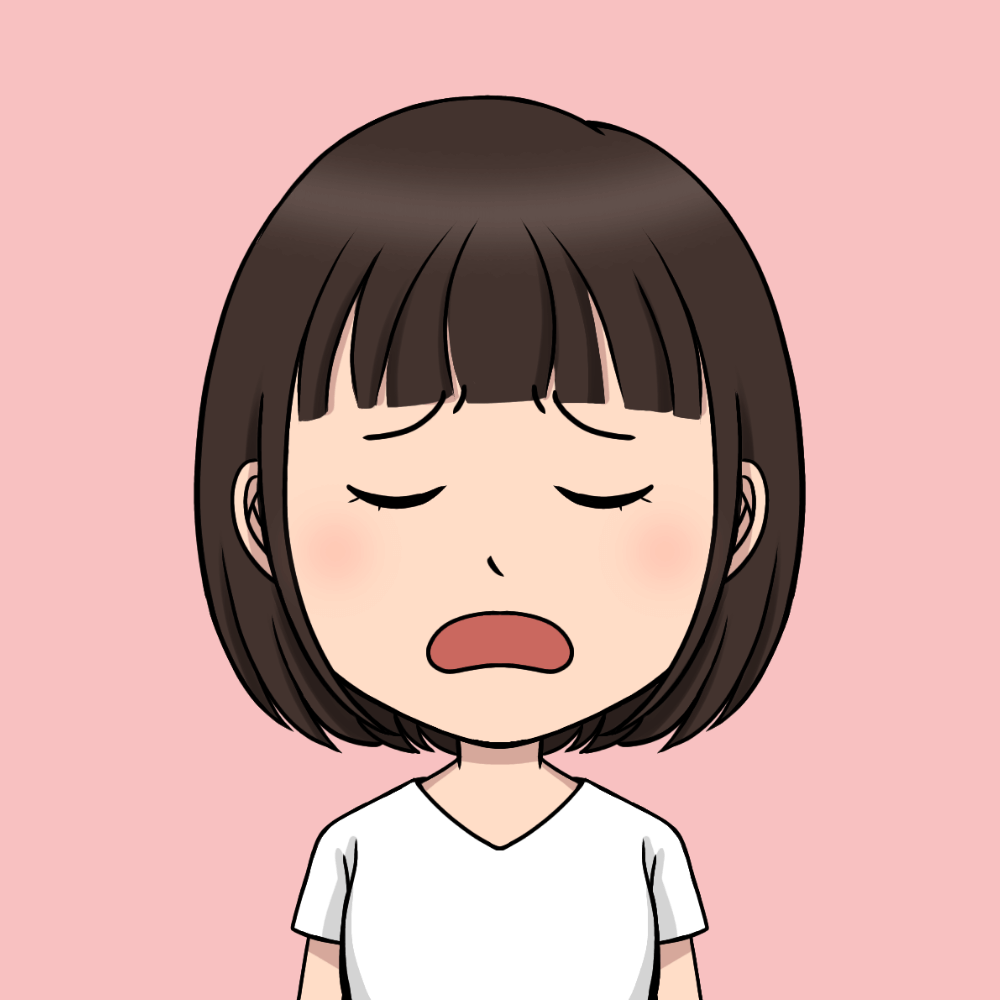
「子どもの課題」と割り切って考えたいけど、子どものしつけや教育は「親の責任」だと非難されるのも事実。周りの目を気にしてしまうこともありますよね。
ここで覚えていて欲しいのは、子供を取り巻く全てを「親の責任」だと考え、子育てに負担を感じる必要はないと言うこと。親子であっても、できること、できないことは違いますし、子どもはそれぞれ個性や特徴を持っています。
子どもの思いに向き合い、前に進もうとするパワー、改善していこうとする姿勢こそ、子育てに負担を感じすぎることなく、快適に子育てをする上で大切なことであると考えています。
子どもがまだ小さい頃は、風呂掃除をする度に「すごいね!」「上手にできたね!」と声かけをしていたお母さん。子どもも成長し、風呂掃除がを当たり前にするようになってからは、風呂掃除をやっただけで褒めることは減っていった。すると、徐々に風呂掃除するのを嫌がるようになり、今ではこちらがお願いしてもやってくれない。
このような場合、手伝いをするかしないかは「子ども自身の課題」と捉えます。
「小さい頃は、よく手伝いをしてくれていたのに、大きくなるにつれて家の手伝いをしなくなった・・・」そんな声をよく聞きます。
子どもは親から褒められるととても嬉しいものです。しかし、褒められることに慣れてしまうと、手伝いをすることではなく、「親に褒められること」が一番の目的になります。その結果、親の期待にそった行動をしようとしてしまうのです。そして親が褒めないと子供は手伝いをしなくなります。
「大きくなったんだからそれぐらいしなさい!」こんな声かけをしてはいませんか?
ここで大切なことは、手伝いをするかどうかは「子供の課題」であるという認識を持つこと。また、手伝いをしてもらったら、「ありがとう」「助かった」と感謝の気持ちを伝えてみてください。
学校から帰宅しても宿題に取り組もうとはせず、だらだらしている。声かけをするが、「後でやるから」と、親の言うことを聞かず、遊んでいる。
このような場合、宿題をするかしないかは「子ども自身の課題」と捉えます。
親が子どもの代わりに勉強しても、意味がありませんし、宿題をしない悩み(子どもの課題)を抱え込むことで、親である私たちが疲れてしまいます。
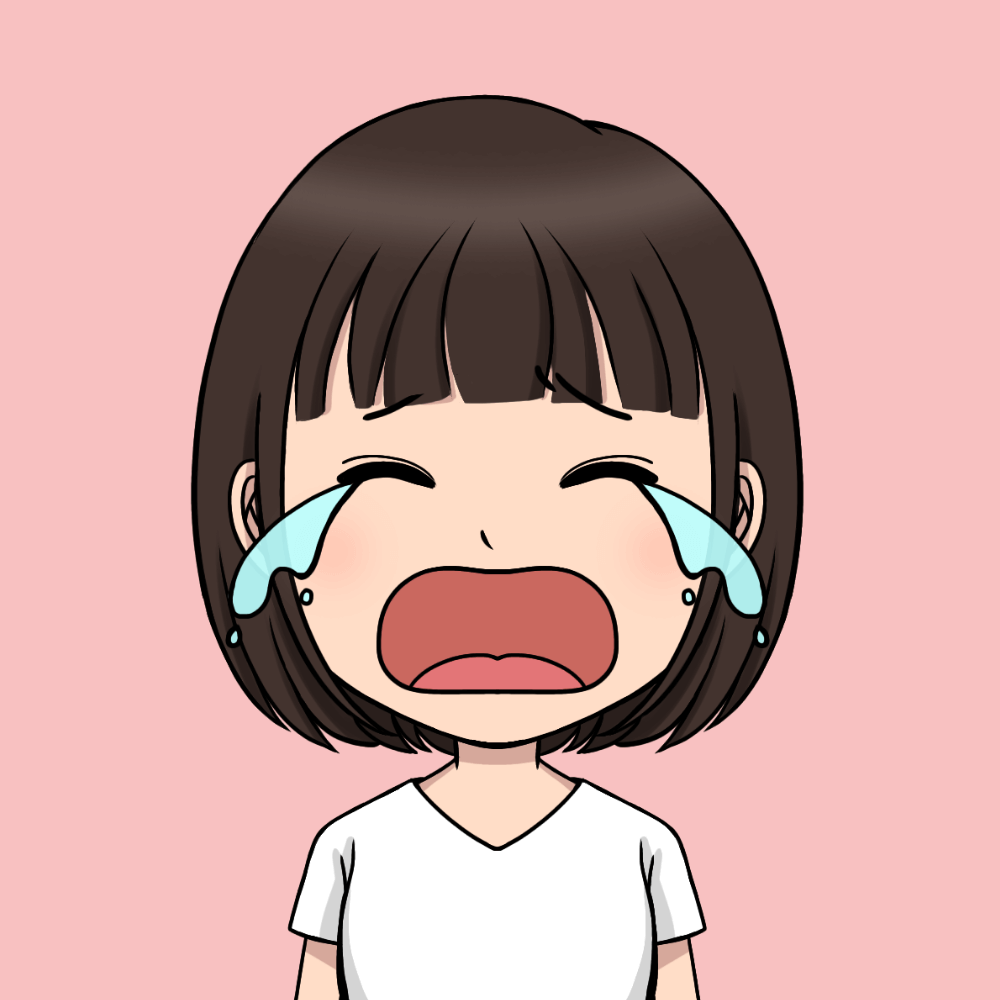
勉強に遅れないようにしなきゃ!周りについて行かなきゃ!と親の方が焦ってしまう気持ちはとてもよくわかります。
しかし、無理に勉強させても身につくわけもなく、反対に子供は反発し、自立心も育まれにくくなり、勉強に対する子どもの意欲を削いでしまうことも。
勉強するかどうかは「子供の課題」であるという認識を持つこと。親である私たちの課題は、子どもの宿題の強制はせず、勉強するように見守ることです。
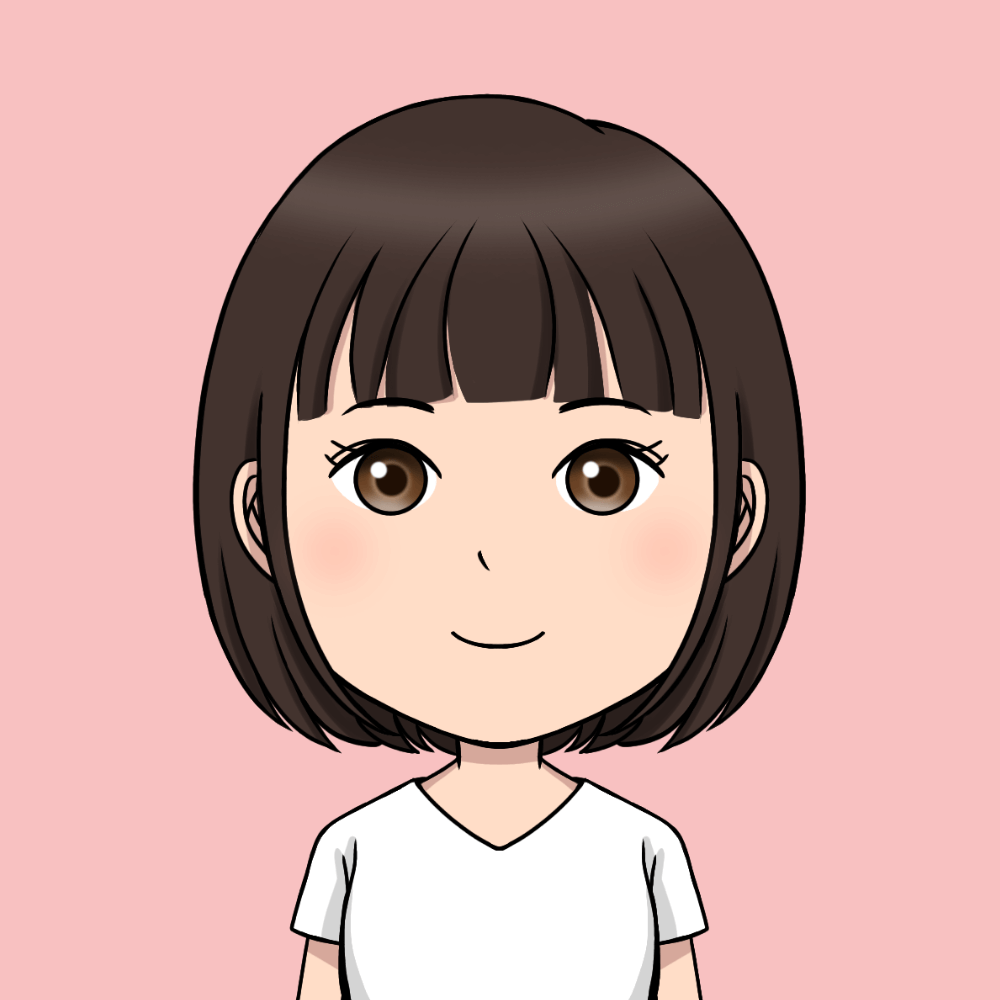
勉強についてはついつい口を出してしまいがち。これからは口うるさく言うのではなく、見守っていきたいと思います。
【対人関係=共同体感覚】感謝の気持ち

他の人を仲間とみなし、そこに自分の居場所があると感じられる「共同体感覚」という考え方。そこに至るためには、横の関係が重要であり、横の関係を築くために「褒めてはいけない」としています。褒めるという行為にはそれだけで、「上から下への評価」という側面が含まれていると言うのです。
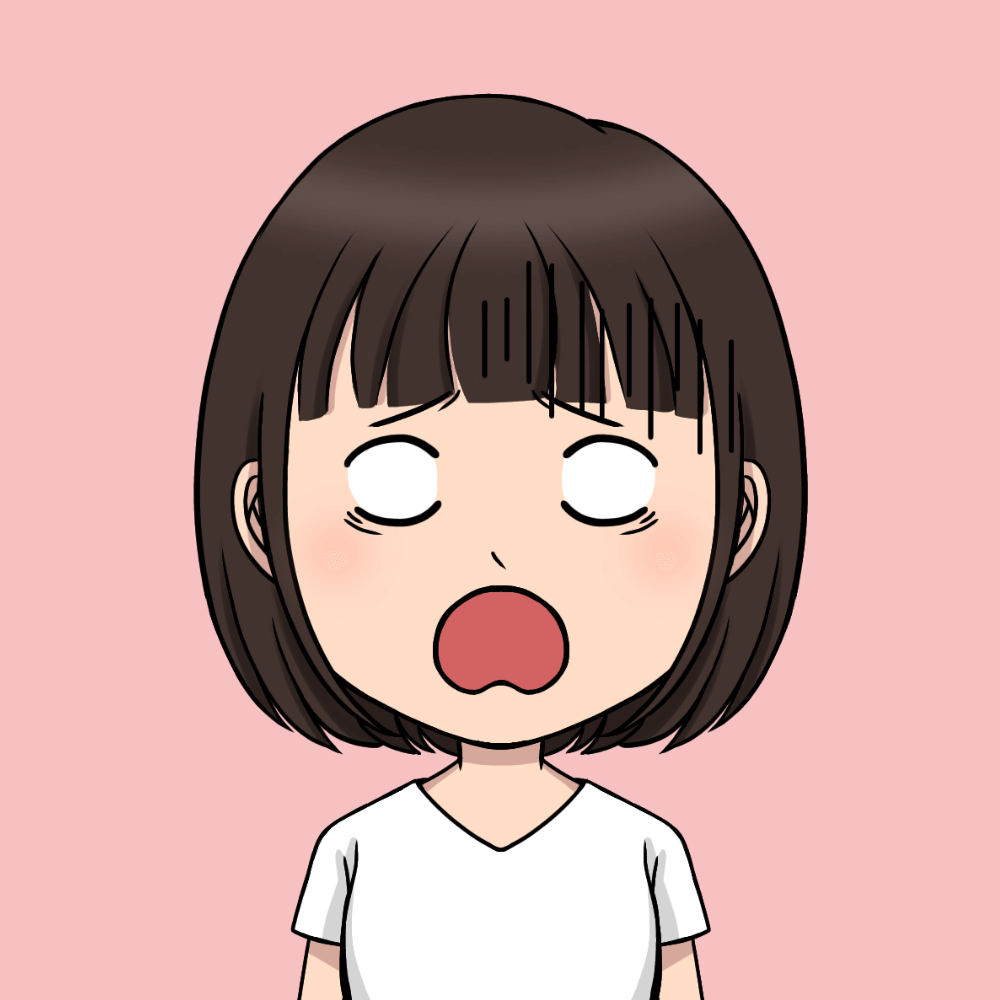
子育てにおいては「褒めて伸ばす」を意識していたからこそ、眼から鱗の言葉でした・・・
【自己肯定感の低い我が子】
物事の出来不出来で周りと比較、評価し育ててしまったこともあり、我が子は自己肯定感が低く、何をするにも「自分はできない」「どうせ失敗する」といつも後ろ向きな姿勢。友達に対しても嫉妬や劣等感を強く持ち、自分に自信が持てない様子。自分を否定したり、周りや自身の成功に対しても歪んだ考えを持つようになってしまった。
「どうせできない」とすぐに諦めてしまう子どもの言葉を聞いては、親である私たちは落ち込んでしまうこともあるかもしれません。このような場合は、我が子が前向きに頑張るきっかけを作ってあげたいと考えるようになります。
ここで大切なのは、子どもと「縦の関係」ではなく「横の関係」を築くこと。
「褒める」のではなく、ありのままの存在を認め、「勇気付け」を行うことは子どもの成長に役立ちます。子どもは、自分が家族の役に立ち感謝をされると、周りに受け入れられ、信頼されるようになり、家庭の中に自分の居場所があると感じられるようにもなります。
「ありがとう」という感謝や尊敬の気持ちを子どもにきちんと伝えることも忘れないでください。「ありがとう」という言葉を一言伝えるだけで、子供は自分の価値を実感でき、満足感でいっぱいになります。
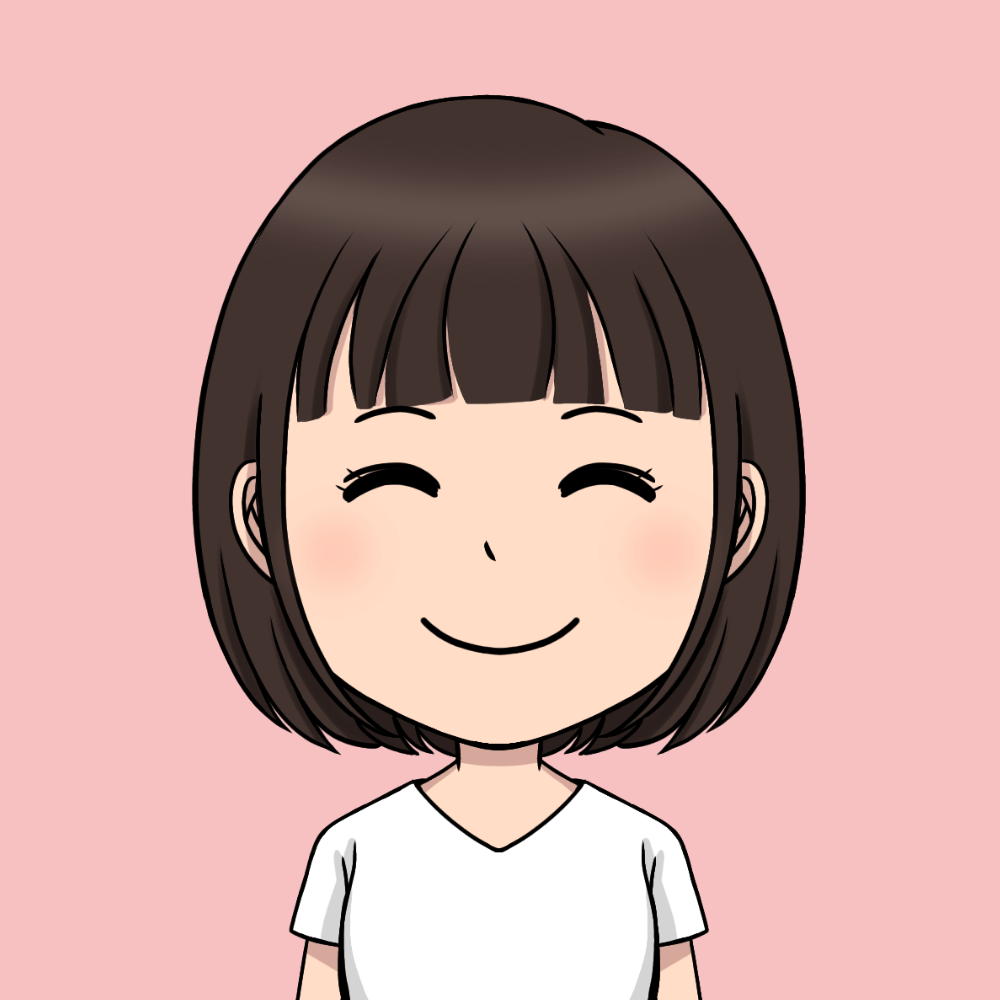
子どもが何事にも自信を持って取り組んでいく姿はとても嬉しいものです。
\関連記事/
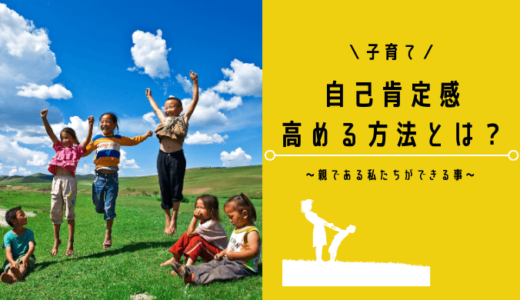 子供の自己肯定感を高めるためには?私たち親ができること
子供の自己肯定感を高めるためには?私たち親ができること
【まとめ】快適な子育てLifeを送ろう
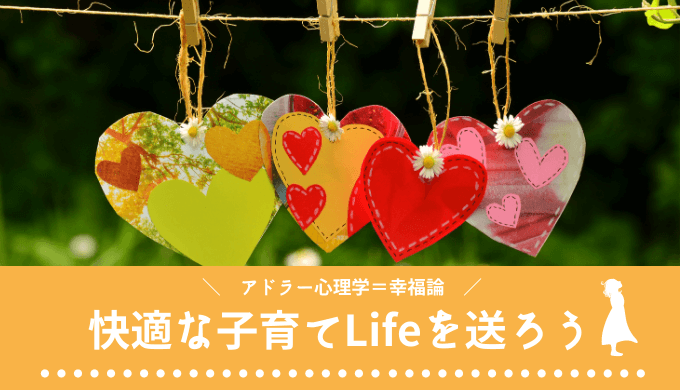
今回は、アドラー心理学を解説した書籍「嫌われる勇気」を読んで学んだことについてまとめました。
子育てをする上で参考になる考え方は、以下の3点。
- 人の悩み→健全な劣等感を持って、子どもの成長を見守る
- 課題の分離→親の課題なのか、子どもの課題なのか見極める
- 対人関係=共同体感覚→褒めるのではなく「感謝する」
私たち親は、「子どものため」と思って働きかけているつもりでも、実際には「子どもの課題」に踏み込んでいる可能性があります。本当に子どものためなのか?今一度自身の胸に問いかけてみてください。
もしかすると、周りからよく見られたい「自分のため」になっているかも知れませんし、そのせいで自分の期待を子どもにかけすぎてしまっているかもしれません。
私たち親に求められることは、子どもに安心感を与えながら、いつでも支援できるよう見守る姿勢です。その線引きはとても難しく、見極めは親である私たちの課題でもあると言えます。
また、子育てにおいては、他の親子との共存も絶対条件として挙げられます。何をするにも、周りの親御さんの目を気にしてはいませんか?
自分や周囲の人のためではなく、「子どものため」に見守り、サポートすることで、子どもが成長するのはもちろん、自分自身も成長し、心地よく暮らしていくきっかけとなります。
幸福論とも言われている「アドラー心理学」
いいなと思ったもの、共感できるものがあればぜひ子育てにも活かしてみてくださいね。
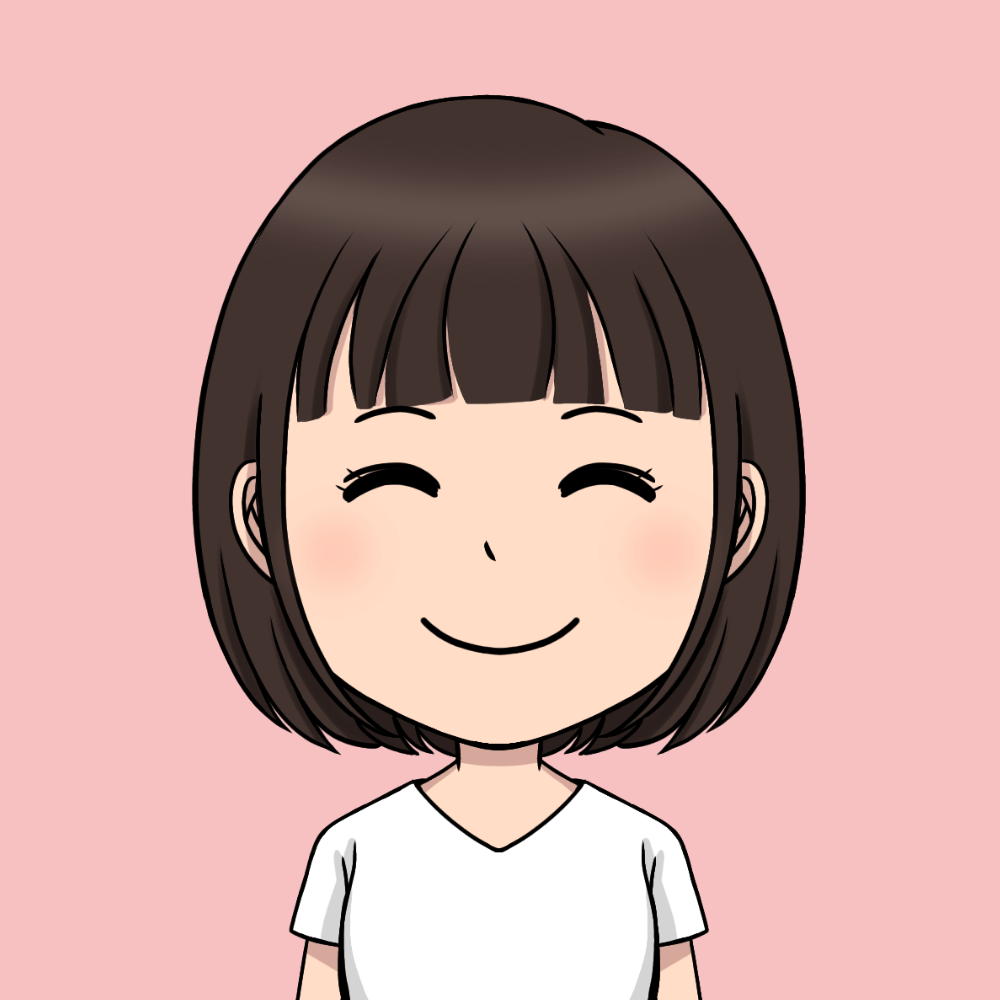
より快適な子育て生活を送っていけるきっかけとなれたら嬉しいです。